

金は今も昔も価値のあるものとして親しまれてきました。
過去日本は世界最大の金の産出国。
金閣寺を建てられたのも、金色堂を建てられたのも豊富な金資源があってこそです。
さらに金を海外へ売って、儲けたお金で西洋の優れた文化をたくさん輸入しました。
結果として日本はアジアの中でも裕福で発展した国になれたという歴史があるのです。
そんな金を掘る道具となるツルハシとツルハシ商人についてビジネスにも応用出来る興味深い話があります。
Sponsored Links
【金山ではツルハシ売りが最も儲かる】
金山や金鉱では、金脈を見つけて一獲千金を手にしようと多くの人が採掘場に集まります。
中には大金持ちになって帰っていく人もいますが、それは一部の強運者だけで実際は宝くじを当てるようなもの。
大金を注ぎ込んで挫折し、借金返済の為に採掘場の労働者として安い賃金で働かされるといった皮肉な結末を迎えた人も少なくありません。
そんな中、採掘場の近くでツルハシを販売していた商人は文字通りツルハシを売って生計を立てていました。
金を掘る人が増えれば増えるほどツルハシが売れ、金脈を当てた人も更に奥へと掘り進むために労働者を増やすのでツルハシを購入してくれます。
気付けば金を掘り当てた人よりもツルハシ商人が一番儲けていた。
と言う話が元になっています。
金を掘る人は当たりハズレがありますが、ツルハシ売りにそんなギャンブル性はありません。
時には金を掘り当てた人から「世話になった」とお礼を受け取ることもあるでしょう。
結果として、
金山ではツルハシ売りが最も儲かる。という構図が出来上がります。

【ビジネスへの応用】
この話をビジネスに置き換えて考えてみましょう。
例えば、最近流行りのLINEスタンプ。
デザイナーがこぞって自作のLINEスタンプを制作して、クリエーターズスタンプとして販売しています。
制作には一定の時間が掛かる上にLINEの規定に沿ったクオリティーも求められます。
最低でも40パターン作らないといけないと言うルールも実際に自作してみると大変な苦労です。
しかし一度人気に火が付けば数十万円、数百万円の収入も夢ではありません。
LINEスタンプの売上の半分が自分に入り、半分がLINE側へ渡るという仕組みなので元手を掛けずに利益を得る事が出来ます。
しかし、この構図で最も儲けているのもまたツルハシ売り(LINEの会社)だったりもするのです。
・スタンプを制作するコスト(時間と労力)
・クオリティーを上げる為の努力
・流行を掴んだ発想などは必要ありません。
極端な話、スタンプを販売出来る環境さえ整えれば、儲けることが出来るのです。
つまり、ツルハシ売りが金を掘れる環境を整えるだけで儲けられるのと仕組みは同じです。
このような事例はスマートフォンアプリ、情報商材、アフィリエイトなどビジネスに応用されています。
【実際には元請けにもコストは掛かる】
しかし、ツルハシ売りの話には盲点があり、在庫や店舗の賃料云々の話は考慮されていません。
LINEスタンプ販売の例も、データを保管しておくサーバー維持費、スタンプの審査をする従業員の人件費などが掛かるので、実際には管理する側にもそれなりのコストは発生しています。
それを踏まえて考えると本当に儲けられるのは金山の近くに土地や建物を持つ不動産屋かもしれませんね。

【編集後記】

ツルハシ売りが店を出して商売をするので、不動産屋が儲かる。
と言うのもある意味ではツルハシ売りの理論が成り立つわけですが…。
なんとも矛盾した例えになってしまいますね(笑)
この話のオチは
『儲けようと一生懸命に働いていてる人より、その人をバックアップする側の方が実は儲けられる』
というところにあります。
ビジネスにおいての自分の立ち位置を意識する事で、意外な収入源が見つかるかもしれませんね。
Sponsored Links
今回のお話が面白いなと思ったらSNSで拡散お願いします(*‘ω‘ *)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
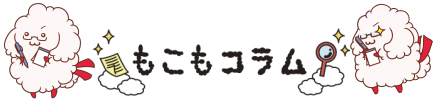
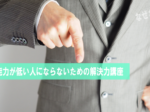





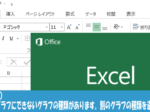

をつけるための習慣を成功者から学ぶ-150x112.png)



この記事へのコメントはありません。